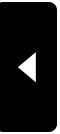2017年05月27日
がん最新情報Ⅹ 簡単にできるがん診断の最近の話題

がん最新情報Ⅹ 簡単にできるがん診断の話題
前回Ⅸのリキッドバイオプシーと同様、尿や血液でがんのリスクを診断する方法で、話題になった2つをご紹介します。
 線虫の嗅覚を利用した「N-NOSEエヌ・ノーズ」
線虫の嗅覚を利用した「N-NOSEエヌ・ノーズ」九州大学の広津たかあき氏らは線虫の鋭い嗅覚を利用して尿一滴で10数種類のがんのリスクを診断する方法を見つけました。(PLOS ONE10(3)2015) これは、がん細胞に特有な分泌物の臭いに線虫が反応し、がん患者の尿の周囲に集まってくることを利用したものです。がん患者24例中23例陽性(感度95.8%)、健常者218例中207例陰性(特異度95.0%)と共に高いものでした。がん患者24例中12例はステージ0~Ⅰ期の早期がんでした。まだがんの種類は同定できませんが、特定のがんにだけ反応しない線虫株を作製しており、将来同定できる可能性があるとしています。
 実用化に向けて日立との共同開発始まる
実用化に向けて日立との共同開発始まる広津氏は株式会社HIROTSUバイオサイエンスを設立していましたが、2017年4月に日立製作所とこの検査の実用化に向けて共同研究開発契約を結びました。今までの人による検査では1日に3~4人しかできませんでしたが、日立は線虫癌検査自動解析装置を新たに開発し、自動化、高速化で2019年末の実用化を目指しています。そして自由診療の枠組みで1回数千円で検査できるようにしたいとしています。
ごく少量の尿で早期がんも高い確率で診断できれば大変喜ばしい事ですので、一刻も早い実用化が望まれますし、癌の種類の診断も期待したいところです。
 7大がんのリスクが一挙に分かる「アミノインデックス検査」
7大がんのリスクが一挙に分かる「アミノインデックス検査」アミノ酸の多くはタンパク質の構成成分で20数種類ありますが、健康な人では血中濃度は常に一定に保たれています。がんになるとそのバランスが崩れてしまう変化を捉えてがんのリスクを判定する検査で、足利工業大学看護学部長の山門實氏(元三井記念病院健診センター長)が味の素と共に開発しました。(日経gooday 2017年4月25日) 例えば,肺がんではグルタミンやヒスチジンなどが減り、オルニチンやセリンが増加します。胃がんではトリプトファンやヒスチジンをはじめ多くのアミノ酸が減ってしまう等です。2011年4月から5年間で約15万人が受けたということです。
チエックできるのは、肺がん、胃がん、大腸がん、膵臓がん、男性はプラス前立腺がんの5種類、女性はプラス乳がん、子宮・卵巣がんの6種類です。(子宮と卵巣がんは区別できません)主要ながんは全て含まれています。結果は通常(1とすると)より低い「ランクA](大阪医大のデーターで0.3~0.7倍)、やや高い「ランクB」(1.3~2.0倍)、高い「ランクC](4.0~10倍)の3段階で示されます。「ランクC]はがんである可能性があるので精密検査が必用ですが、実際にがんが発見されるのは約100人に1人です。三井記念病院の5172人の解析では、がん発見率は0.33%(1000人に3~4人)でした。人間ドック全国集計(2015年)の発見率0.26%より高く、その殆どが早期がんだったとしています。(山門)
検査は5mlの採血で、費用は約25000円です。この検査を受けられる医療機関は[http://search.aminoindex.jp/]で検索できます。
アミノインデックスはどのがんのリスクが高いかわかるメリットがありますが、高リスクの人の癌の率は1%で感度は低いようです。しかし「ランクC]とされたらやはり精密検査を受けないと心配ですね。
(文責 篠原)
2017年04月30日
がん最新情報Ⅸ 血液だけでがんの早期診断ができる時代が来る!!

がん最新情報Ⅸ 血液だけでがんの早期診断ができる時代が来る!!
がんの早期診断には検診・ドックが奨められていますが、これには“めんどうくさい” “体に負担がかかって辛い”等、何らかの抵抗感がある事は否めません。もし、血液、尿、唾液を少量取るだけで早期診断ができるようになったらどんなに素晴らしいことでしょう。これをリキッドー液体の意味ー・バイオプシーと言います。これが可能となる時代がもうすぐ来そうです。
 血液一滴でがん早期診断
血液一滴でがん早期診断国立がん研究センターの落谷氏らは2015年「体液中のマイクロRNA(miRNA)測定技術基盤開発プロジェクト」を立ち上げ、2018年度末迄に10種類以上のがんの早期診断を目指す、と発表しました。(第20回国際個別化医療学会)
がん細胞はじめ殆どの細胞が体液中にエクソソームという物質を分泌し、循環しています。この中には核酸(DNAやmiRNA)も内包されています。がん細胞に特異的な分子を検出すれば、早期がんの診断が可能になる訳です。
miRNAを利用して乳がんの解析が現在迄1000例以上と先行しており、感度(がんの人が陽性になる率)、特異度(癌でない人が陰性になる率)共99%以上と非常に高く、直径3mmの乳がんも診断できたとしています。
乳がんは術後10~20年に再発、転移する例もありますが、これは「正常細胞が分泌するエクソソームを乳がん細胞が横取りして、これにより骨髄中で休眠状態を保ち生存していた。」事が判ってきました。
いずれは尿や唾液でも早期診断できるようにしたいとしており、尿に含まれるエクソソームを使って膀胱がんを検出する可能性も示唆されています。
 大腸がんの早期スクリーニング法を開発
大腸がんの早期スクリーニング法を開発神戸大のグループは血液中の代謝物バイオマーカーを高精度に定量できる分析法を開発し、これによって早期の大腸がん診断予測式を作製しました。バイオマーカーは、ピルビン酸、グリコール酸、トリプトファン、パルミトレイン酸、フマル酸、オルニチン、リシン、3-ビロキシイソ吉草酸の代謝物8種類です。
この結果、感度、特異度共96%を超えたとし、ステージ0~Ⅰ期の早期がんでも高い感度だったとしています。(Oncotarget オンライン版2017年)
 リキッド・バイオプシーのその他の有用性
リキッド・バイオプシーのその他の有用性肺がんの抗癌剤ゲフイニチブ(イレッサ)の耐性(薬の効果が無くなること)の50~60%はEGFR(上皮成長因子受容体)の「T790M」という遺伝子変異によりおきています。この変異の有無とオシメルチニブ(タグリッソ)の有効性を血液で調べる診断薬「コバスEGFR変異検出キット」が2016年12月に認められました。がん組織を採取できない~むつかしい患者さんにとって、体に負担の無い大きな利点があります。又、エクソソームはがんの増殖、転移を制御したり、悪化に関わることが判っていますので、この方面の研究にも期待されます。
 前回(がん最新情報Ⅷ がん死亡は減らせるか?の最後に述べたように、がんは多くが偶然の遺伝子変異により発生し、、誰がなってもおかしくありません。。リキッド・バイオプシーのように簡単にできる検査で、もしなっても完治できるような早期診断法が今最も望まれています。
前回(がん最新情報Ⅷ がん死亡は減らせるか?の最後に述べたように、がんは多くが偶然の遺伝子変異により発生し、、誰がなってもおかしくありません。。リキッド・バイオプシーのように簡単にできる検査で、もしなっても完治できるような早期診断法が今最も望まれています。(文責 篠原)
2017年04月09日
がん最新情報Ⅷ がん死亡は減らせるか?-国のがん対策の課題はー
がん最新情報Ⅷ がん死亡は減らせるか?
がんは1981年以来日本の死因第1位です。国は2007年4月「がん対策基本法」を施行し、「がん対策推進基本計画」を策定しました。今年第3期計画を策定します。
当初の「がんによる75歳未満の年齢調整死亡率*の20%減少」の目標は17%減に留まり(2015年予測)、目標を達成できませんでした。次の10年で癌死亡をどのくらい減らせるのか、幾つか課題を考えます。(国立がん研究センターがん対策情報センター 加藤、籐下 医学界新聞 2017年1月2日号を参考にしました。)
*昭和60年の年齢構成を基準にして補正した死亡率
 がん予防の観点から
がん予防の観点から
予防の第一は喫煙対策
日本の研究では男性で約30%、女性で5%が喫煙が原因です。特に肺がん死亡の原因は男性70%、女性20%と言われています。受動喫煙による肺がんのリスクは,ない人の約1.3倍高いとの結果がでています。居酒屋やスナックなどの小さい店も全面禁煙にする法案が出されましたが、反対もあり簡単に決まりそうにありません。死亡者数1位の肺がんを減らすには喫煙対策が最重要です。
肥満・運動不足によるリスク
肥満とがんの関係を多くの研究から分析した報告があります。強力なエビデンス(科学的な根拠)があったのは、食道腺がん、胃噴門がん、結腸がん、直腸がん、胆道系がん、膵臓がん、乳がん、子宮内膜がん、卵巣がん、腎臓がん、多発性骨髄腫の11のがんでした。例えば、男性の結腸・直腸がんはBMI*が5増加するごとにリスクは9%上昇、胆道系がんは56%上昇、閉経女性の乳がんは成人期の体重5Kg増加するごとに11%の上昇でした(MariaKyrgiou BMJ2017)。過度の体重増加には気をつけたほうが良いようです。
*BMI(BodyMassIndex) 肥満の程度を示す指標の一つ 体重(Kg)÷身長(m)×身長(m) 標準は18.5~24.9)
 がん検診の観点から
がん検診の観点から
2008年から市町村の事業としてがん検診が実施されています。5年以内に受診率50%を目標にしましたが、2013年で40%程度で、外国の70~80%に比べてもかなり低い状況です。
検診方法についても検討を要するものがあります。(肺がん検診については、本ブログ内「肺がん検診は今のままで良いか」をご覧下さい)
最近問題になっているのが乳がん検診です。現在2年に1回マンモグラフィーが推奨されています。しかし、日本人の5~8割に当たる高濃度乳腺は全体が白く映ってしまい、異常が見つけ難いのです。これを受診者に通知している自治体は全国で23と少ないのです(読売新聞2017年2月)。静岡市はじめ県内では未だ対策をとっている所はありません。今後は超音波(US)検査の併用も検討する必要があるでしょう。
 がん治療病院の観点から
がん治療病院の観点から
どこに住んでいてもレベルの高い医療を受けられる事を目的として、国は2001年度に「がん診療連携拠点病院」を創設しました。2017年1月現在400の病院が指定されています。
2008年に静岡県立がんセンターの山口らが現状と課題を発表しました。「機能の全てが期待どうりに、又実質的に稼働しているかと問われれば、否とする施設が多いだろう」 「がん医療の専門医-特に緩和ケア、放射線治療、病理医ー、看護師、技師の慢性的な不足」 「補助金が十分でない」等の問題を指摘しています。その後改善が進んでいると思いますが、実態を把握して、適切な医療が提供されているか検証が必要です。さらに、米国等に比べて遅れているゲノム医療*に代表される先端医療の取り組みも早急に望まれます。
*がん遺伝子解析により、超早期診断や、個々の患者に合った最適な医療の提供
 がんになるのは本人の責任か?
がんになるのは本人の責任か?
タバコは吸わない、お酒は適量、運動もして健康に気をつけていてもがんになる人は少なくありません。「どうして自分が?」と嘆きたくなるでしょう。この答えの一つになる論文がでました。(米ジョンズ・ホプキンス大学 Science 2017年3月24日号)
これによると、「がんの多く、3分の2は偶然の遺伝子の変異に因ずく」 「正常な細胞が分裂してDNAが複製され、2つの新しい細胞ができるたびに多くのミスが生じている」 「肺がんは生活習慣や環境による影響が大きく、65%が喫煙などに起因し、ミスによるものは35%。膵臓がんの77%は偶然の突然変異により発生し、18%が環境因子、5%が両親からの遺伝的要因」 「32種類のがん全体では環境要因は29%にすぎず、どんなに環境や生活習慣に配慮してもがんは防げない」としています。
健康的な生活を心がけていたのになぜ?と悩むがん患者さんには、「がんになったのは本人に責任がない。」が少し慰めになるでしょうか。 (文責 篠原)
がんは1981年以来日本の死因第1位です。国は2007年4月「がん対策基本法」を施行し、「がん対策推進基本計画」を策定しました。今年第3期計画を策定します。
当初の「がんによる75歳未満の年齢調整死亡率*の20%減少」の目標は17%減に留まり(2015年予測)、目標を達成できませんでした。次の10年で癌死亡をどのくらい減らせるのか、幾つか課題を考えます。(国立がん研究センターがん対策情報センター 加藤、籐下 医学界新聞 2017年1月2日号を参考にしました。)
*昭和60年の年齢構成を基準にして補正した死亡率
 がん予防の観点から
がん予防の観点から予防の第一は喫煙対策
日本の研究では男性で約30%、女性で5%が喫煙が原因です。特に肺がん死亡の原因は男性70%、女性20%と言われています。受動喫煙による肺がんのリスクは,ない人の約1.3倍高いとの結果がでています。居酒屋やスナックなどの小さい店も全面禁煙にする法案が出されましたが、反対もあり簡単に決まりそうにありません。死亡者数1位の肺がんを減らすには喫煙対策が最重要です。
肥満・運動不足によるリスク
肥満とがんの関係を多くの研究から分析した報告があります。強力なエビデンス(科学的な根拠)があったのは、食道腺がん、胃噴門がん、結腸がん、直腸がん、胆道系がん、膵臓がん、乳がん、子宮内膜がん、卵巣がん、腎臓がん、多発性骨髄腫の11のがんでした。例えば、男性の結腸・直腸がんはBMI*が5増加するごとにリスクは9%上昇、胆道系がんは56%上昇、閉経女性の乳がんは成人期の体重5Kg増加するごとに11%の上昇でした(MariaKyrgiou BMJ2017)。過度の体重増加には気をつけたほうが良いようです。
*BMI(BodyMassIndex) 肥満の程度を示す指標の一つ 体重(Kg)÷身長(m)×身長(m) 標準は18.5~24.9)
 がん検診の観点から
がん検診の観点から2008年から市町村の事業としてがん検診が実施されています。5年以内に受診率50%を目標にしましたが、2013年で40%程度で、外国の70~80%に比べてもかなり低い状況です。
検診方法についても検討を要するものがあります。(肺がん検診については、本ブログ内「肺がん検診は今のままで良いか」をご覧下さい)
最近問題になっているのが乳がん検診です。現在2年に1回マンモグラフィーが推奨されています。しかし、日本人の5~8割に当たる高濃度乳腺は全体が白く映ってしまい、異常が見つけ難いのです。これを受診者に通知している自治体は全国で23と少ないのです(読売新聞2017年2月)。静岡市はじめ県内では未だ対策をとっている所はありません。今後は超音波(US)検査の併用も検討する必要があるでしょう。
 がん治療病院の観点から
がん治療病院の観点からどこに住んでいてもレベルの高い医療を受けられる事を目的として、国は2001年度に「がん診療連携拠点病院」を創設しました。2017年1月現在400の病院が指定されています。
2008年に静岡県立がんセンターの山口らが現状と課題を発表しました。「機能の全てが期待どうりに、又実質的に稼働しているかと問われれば、否とする施設が多いだろう」 「がん医療の専門医-特に緩和ケア、放射線治療、病理医ー、看護師、技師の慢性的な不足」 「補助金が十分でない」等の問題を指摘しています。その後改善が進んでいると思いますが、実態を把握して、適切な医療が提供されているか検証が必要です。さらに、米国等に比べて遅れているゲノム医療*に代表される先端医療の取り組みも早急に望まれます。
*がん遺伝子解析により、超早期診断や、個々の患者に合った最適な医療の提供
 がんになるのは本人の責任か?
がんになるのは本人の責任か?タバコは吸わない、お酒は適量、運動もして健康に気をつけていてもがんになる人は少なくありません。「どうして自分が?」と嘆きたくなるでしょう。この答えの一つになる論文がでました。(米ジョンズ・ホプキンス大学 Science 2017年3月24日号)
これによると、「がんの多く、3分の2は偶然の遺伝子の変異に因ずく」 「正常な細胞が分裂してDNAが複製され、2つの新しい細胞ができるたびに多くのミスが生じている」 「肺がんは生活習慣や環境による影響が大きく、65%が喫煙などに起因し、ミスによるものは35%。膵臓がんの77%は偶然の突然変異により発生し、18%が環境因子、5%が両親からの遺伝的要因」 「32種類のがん全体では環境要因は29%にすぎず、どんなに環境や生活習慣に配慮してもがんは防げない」としています。
健康的な生活を心がけていたのになぜ?と悩むがん患者さんには、「がんになったのは本人に責任がない。」が少し慰めになるでしょうか。 (文責 篠原)
2017年02月24日
がん最新情報Ⅶ 肝臓がんQ&A
がん最新情報Ⅶ 肝臓がんQ&A
 肝臓がんの原因、予後、特徴
肝臓がんの原因、予後、特徴
Q1 肝臓がんの原因は何ですか?
A1 約90%がB型、C型肝炎ウイルスの長期かつ継続的な感染が原因です。
Q2 早期に発見できますか?
A2 早期に症状はありませんが、ウイルス感染が陽性で定期的なチエックで早 期に発見できます。事実、Ⅰ期(がんが1個、大きさ2cm以下、脈管浸潤なし)で44%、Ⅱ期(先の内2項目は相当)で24%で、3分の2が比較的早期に発見されています。
Q3 予後はどうですか?
A3 5年生存率32.2%、10年生存率15.3%と良くありません。5年過ぎても生存率が大きく低下し続けるがんは他にありません。
Q4 なぜそんなに予後が悪いのですか?
A4 再発率が高い(5年で80%位再発)からで、これが肝臓がんの特徴です。最初からあちこちに多発しているという説もあります。
 肝臓がんの治療
肝臓がんの治療
Q5 切除手術の適応は
A5 肝障害度(後述)A,Bで数が3個以下であれば切除手術の適応になります。
Q6 がんの大きさは関係ないのですか?
A6 ガイドラインでは大きさの規定はありません。しかし、慢性肝炎や肝硬変がベースにありますから、取りすぎると術後肝不全から死にいたることもありますので、術前の十分な検索が必用です。
Q7 腹腔鏡下手術は行われますか?
A7 肝臓は解剖学的に8つの亜区域に分けられます。2016年に2~3区域(右葉も)切除が保険で認められましたので、大きい腫瘍や複数個のがんも可能になりました。
Q8 ラジオ波焼却療法(RFA)とはどんな治療法ですか?
A8 体表から電極針をがんまで刺して通電し、先端部に100°Cの高熱を発生させてがんを焼く治療です。2004年から保険が適用されました。大きさ3cm以下、3個迄が一応の目安です。1回の通電時間は10~20分です。
Q9 RFAの成績はどうですか?
A9 日本でトップクラスの施行例を持つ東京大学の15年間、約8000件の内初発例1616例の成績です。(建石:52回日本肝臓学会2016)
3年時 5年時 10年時
全生存率 62.3% 28.2%
再発率 68.5% 81.4% 89.5%
局所再発率 4.0% 4.1%
全国の10年生存率は、Ⅰ期約30%、Ⅱ期17%ですから、長期生存を期待させる成績と思われます。
2014年の平均腫瘍径は17.1mmで、「小さい腫瘍なら1回の治療で終了する。」「主要な治療法として今後も大きな役割を果たしていく。」としています。
Q10 RFAに危険性はありませんか?
A10 重症な合併症(腹腔内出血、胆道出血等)は1999年当初から約3%と低く、現在は1%未満です。(建石)全身への負担が少なく、比較的安全に何回もできるのが特徴です。
Q11 初めての治療で(3cm以下で3個以内)切除とRFAのどちらを選択したらいいでしょう?
A11 両者の成績に差がないという報告もあるようですが、議論のあるところで、今後さらに検討が必要です。
Q12 RFAはどこの病院で行っていますか?
A12 静岡県内では、県立がんセンター、県立総合病院、順天堂静岡病院、富士市立中央病院等が年40件以上の経験があります。(読売新聞医療部編「病院の実力」2016年から)
Q13 再発に対して再切除は可能ですか?
A13 根治的肝切除後の再発で再切除を行った146例の報告です。(山下:九州がんセンター EuropeanCancerCongress2015
)
(全)再切除例 肝障害度A 肝障害度B
5年生存率 75% 77% 20%
5年無再発生存率 16% 21% 0%
肝障害度分類(日本肝癌研究会2009年)
A B C
腹水 なし 治療効果あり 治療効果少ない
血清ビリルビン(mg/dl) <2.0 2.0~3.0 >3.0
血清アルブミン(g/dl) >3.5 3.0~3.5 <3.0
ICGR15(%) <15 15~40 >40
プロトロンビン活性(%) >80 50~80 <50
肝障害度Aに比べてBは生存率が極端に低いです。肝障害が比較的軽いAは再切除を選択できますが、B~Cは他の治療(RFA、血管塞栓術、肝移植等)を選択したほうがいい結果です。
 肝臓がんで死なないために
肝臓がんで死なないために
肝臓がんになったら一生“再発との戦い”を強いられることになります。まずならないこと、もしなっても小さい内に発見することが大切です。
Q14 肝臓がんにならないためにはどうしたらいい?
A14 B,C肝炎ウイルス検査(血液検査)を一度は必ず受けましょう。(自治体で無料でできます。)もし陽性ならウイルス根絶の治療を受けましょう。定期的な検査を継続(ウイルスが消失した後も)しましょう。
(文責 篠原)
 肝臓がんの原因、予後、特徴
肝臓がんの原因、予後、特徴Q1 肝臓がんの原因は何ですか?
A1 約90%がB型、C型肝炎ウイルスの長期かつ継続的な感染が原因です。
Q2 早期に発見できますか?
A2 早期に症状はありませんが、ウイルス感染が陽性で定期的なチエックで早 期に発見できます。事実、Ⅰ期(がんが1個、大きさ2cm以下、脈管浸潤なし)で44%、Ⅱ期(先の内2項目は相当)で24%で、3分の2が比較的早期に発見されています。
Q3 予後はどうですか?
A3 5年生存率32.2%、10年生存率15.3%と良くありません。5年過ぎても生存率が大きく低下し続けるがんは他にありません。
Q4 なぜそんなに予後が悪いのですか?
A4 再発率が高い(5年で80%位再発)からで、これが肝臓がんの特徴です。最初からあちこちに多発しているという説もあります。
 肝臓がんの治療
肝臓がんの治療Q5 切除手術の適応は
A5 肝障害度(後述)A,Bで数が3個以下であれば切除手術の適応になります。
Q6 がんの大きさは関係ないのですか?
A6 ガイドラインでは大きさの規定はありません。しかし、慢性肝炎や肝硬変がベースにありますから、取りすぎると術後肝不全から死にいたることもありますので、術前の十分な検索が必用です。
Q7 腹腔鏡下手術は行われますか?
A7 肝臓は解剖学的に8つの亜区域に分けられます。2016年に2~3区域(右葉も)切除が保険で認められましたので、大きい腫瘍や複数個のがんも可能になりました。
Q8 ラジオ波焼却療法(RFA)とはどんな治療法ですか?
A8 体表から電極針をがんまで刺して通電し、先端部に100°Cの高熱を発生させてがんを焼く治療です。2004年から保険が適用されました。大きさ3cm以下、3個迄が一応の目安です。1回の通電時間は10~20分です。
Q9 RFAの成績はどうですか?
A9 日本でトップクラスの施行例を持つ東京大学の15年間、約8000件の内初発例1616例の成績です。(建石:52回日本肝臓学会2016)
3年時 5年時 10年時
全生存率 62.3% 28.2%
再発率 68.5% 81.4% 89.5%
局所再発率 4.0% 4.1%
全国の10年生存率は、Ⅰ期約30%、Ⅱ期17%ですから、長期生存を期待させる成績と思われます。
2014年の平均腫瘍径は17.1mmで、「小さい腫瘍なら1回の治療で終了する。」「主要な治療法として今後も大きな役割を果たしていく。」としています。
Q10 RFAに危険性はありませんか?
A10 重症な合併症(腹腔内出血、胆道出血等)は1999年当初から約3%と低く、現在は1%未満です。(建石)全身への負担が少なく、比較的安全に何回もできるのが特徴です。
Q11 初めての治療で(3cm以下で3個以内)切除とRFAのどちらを選択したらいいでしょう?
A11 両者の成績に差がないという報告もあるようですが、議論のあるところで、今後さらに検討が必要です。
Q12 RFAはどこの病院で行っていますか?
A12 静岡県内では、県立がんセンター、県立総合病院、順天堂静岡病院、富士市立中央病院等が年40件以上の経験があります。(読売新聞医療部編「病院の実力」2016年から)
Q13 再発に対して再切除は可能ですか?
A13 根治的肝切除後の再発で再切除を行った146例の報告です。(山下:九州がんセンター EuropeanCancerCongress2015
)
(全)再切除例 肝障害度A 肝障害度B
5年生存率 75% 77% 20%
5年無再発生存率 16% 21% 0%
肝障害度分類(日本肝癌研究会2009年)
A B C
腹水 なし 治療効果あり 治療効果少ない
血清ビリルビン(mg/dl) <2.0 2.0~3.0 >3.0
血清アルブミン(g/dl) >3.5 3.0~3.5 <3.0
ICGR15(%) <15 15~40 >40
プロトロンビン活性(%) >80 50~80 <50
肝障害度Aに比べてBは生存率が極端に低いです。肝障害が比較的軽いAは再切除を選択できますが、B~Cは他の治療(RFA、血管塞栓術、肝移植等)を選択したほうがいい結果です。
 肝臓がんで死なないために
肝臓がんで死なないために肝臓がんになったら一生“再発との戦い”を強いられることになります。まずならないこと、もしなっても小さい内に発見することが大切です。
Q14 肝臓がんにならないためにはどうしたらいい?
A14 B,C肝炎ウイルス検査(血液検査)を一度は必ず受けましょう。(自治体で無料でできます。)もし陽性ならウイルス根絶の治療を受けましょう。定期的な検査を継続(ウイルスが消失した後も)しましょう。
(文責 篠原)
2017年01月31日
(続)予後の悪い膵臓がんへの挑戦
(続)予後の悪い膵臓がんへの挑戦
前回の記事からご覧いただけたら幸いです。
 5年生存率20%を達成した尾道方式
5年生存率20%を達成した尾道方式
尾道市の広島厚生連尾道病院と尾道医師会が連携した「早期膵がんスクリーニング事業」の結果が発表されました。(日経メヂカルCancerReview,カバーストーリー1、2017年1月)
まず、危険因子を持つ人に市内の開業医で腹部超音波検査を受けてもらい、疑わしい症例を病院で精査するシステムを作りました。病院ではEUS(USを先端に付けた内視鏡)とCT等を行います。この結果2007年から2014年迄に6475人の疑い症例から399人のがんを発見しました。早期はⅠ期16例、Ⅱ期は17例でした。そして5年生存率約20%を達成しました。全国平均が7.5~7.7%ですから、非常に高い生存率です。
又、スウエーデンの会社と連携して早期(腫瘍)マーカーの探索にも取り組んでいます。連携先のImmunovia社のBorrebaeck氏は、「手術可能なⅠ/Ⅱ期患者に特徴的な25種のタンパク質を特定し、この時期の膵臓がんを96%の精度で検出できる事を確認した。」と述べています。
 膵臓がんの高リスク(危険因子)の人とは
膵臓がんの高リスク(危険因子)の人とは
膵臓は血糖と密接に関連しています。膵臓がんから糖尿病を発症した人もいますので、糖尿病と診断された人はUSとCT検査を受けることをお薦めします。糖尿病(治療中の人も)が急に悪化した人、慢性膵炎の人、家族内に膵臓がんのいる人も高リスクです。
 膵臓がんの予後改善に光明が見えてきた!?
膵臓がんの予後改善に光明が見えてきた!?
「遅くとも手術不能になる前にみつけたい。」という尾道病院の花田氏らの思いと努力が生存率の大きな改善に繋がったと思います。
症状のない高リスクの人に検査を受けてもらうことがまず第一ですから、一般開業医、特に消化器医の努力が大切です。USは苦痛の無い検査ですが、膵臓はその位置関係から描出が難しい例もあります。市民への啓蒙と、確かなUSの技術と読影力を持った医師の拡充、確保が必要です。この尾道方式が全国に拡がつて膵臓がんの予後が改善される事を願っています。又、新しい腫瘍マーカーが早く実用化されて、臨床の場に登場することが期待されます。(文責 篠原)
前回の記事からご覧いただけたら幸いです。
 5年生存率20%を達成した尾道方式
5年生存率20%を達成した尾道方式尾道市の広島厚生連尾道病院と尾道医師会が連携した「早期膵がんスクリーニング事業」の結果が発表されました。(日経メヂカルCancerReview,カバーストーリー1、2017年1月)
まず、危険因子を持つ人に市内の開業医で腹部超音波検査を受けてもらい、疑わしい症例を病院で精査するシステムを作りました。病院ではEUS(USを先端に付けた内視鏡)とCT等を行います。この結果2007年から2014年迄に6475人の疑い症例から399人のがんを発見しました。早期はⅠ期16例、Ⅱ期は17例でした。そして5年生存率約20%を達成しました。全国平均が7.5~7.7%ですから、非常に高い生存率です。
又、スウエーデンの会社と連携して早期(腫瘍)マーカーの探索にも取り組んでいます。連携先のImmunovia社のBorrebaeck氏は、「手術可能なⅠ/Ⅱ期患者に特徴的な25種のタンパク質を特定し、この時期の膵臓がんを96%の精度で検出できる事を確認した。」と述べています。
 膵臓がんの高リスク(危険因子)の人とは
膵臓がんの高リスク(危険因子)の人とは膵臓は血糖と密接に関連しています。膵臓がんから糖尿病を発症した人もいますので、糖尿病と診断された人はUSとCT検査を受けることをお薦めします。糖尿病(治療中の人も)が急に悪化した人、慢性膵炎の人、家族内に膵臓がんのいる人も高リスクです。
 膵臓がんの予後改善に光明が見えてきた!?
膵臓がんの予後改善に光明が見えてきた!?「遅くとも手術不能になる前にみつけたい。」という尾道病院の花田氏らの思いと努力が生存率の大きな改善に繋がったと思います。
症状のない高リスクの人に検査を受けてもらうことがまず第一ですから、一般開業医、特に消化器医の努力が大切です。USは苦痛の無い検査ですが、膵臓はその位置関係から描出が難しい例もあります。市民への啓蒙と、確かなUSの技術と読影力を持った医師の拡充、確保が必要です。この尾道方式が全国に拡がつて膵臓がんの予後が改善される事を願っています。又、新しい腫瘍マーカーが早く実用化されて、臨床の場に登場することが期待されます。(文責 篠原)
2017年01月29日
がん最新情報Ⅵ ー予後の悪い膵臓がんへの挑戦ー

がん最新情報Ⅵ 予後の悪い膵臓がんへの挑戦
 生存率が最も悪い膵臓がん
生存率が最も悪い膵臓がん膵臓がんの患者数は約4万人で日本の癌の7位ですが、死亡数(2016年の予測)は男性17100人、女性16600人、計33700人で4位です。5年(相対)生存率は7.7~9.1%、10年生存率は4.9%で最も低く、予後の悪いがんです。(国立がん研究センター2016年)しかも、多くのがんは1993年以後生存率が上昇傾向ですが、膵臓がんは横ばいで殆ど改善されていません。
 どうして予後が悪いのか
どうして予後が悪いのか膵臓がんには特有の症状がありません。腹痛、背部痛、痩せてきた、食欲不振、黄疸等はかなり進行してからでてくる症状です。0-Ⅰ期(膵管上皮内がんー2cm以内でリンパ転移なし)で発見されるのはわずか12%で、Ⅳ期(周囲に浸潤/リンパ転移あり)が43%を占めることからも早期診断の困難さが判ります。
又、膵臓はお腹の深い所にあって、簡単に検査ができない事も原因の一つです。 (続く)
(文責 篠原)
2017年01月16日
がん最新情報Ⅴー(続々)遺伝しやすい乳がんとはー
訂正 前回の記事に誤りがありました。下記のように訂正いたします。
遺伝子検査 (誤)2000~3000円→(正)20~30万円
前々回の記事からご覧いただけましたら幸いです。
がん最新情報Ⅴ(続々)遺伝しやすい乳がんとは
 アンジェリーナ・ジョリーさんの手術後、何か変化あったか
アンジェリーナ・ジョリーさんの手術後、何か変化あったか
ジョリーさんの手記は2013年5月にニユーヨークタイムズ誌に掲載されました。その前後で検査を受けた人、切除を受けた人数に変化があったかどうかの調査報告が出ました。
対象は2012~13年に保険に加入していた18~64歳の女性953万人余人です。
遺伝子(BRCA)検査の受診率は掲載前の10万人当たりO.71人/日から後は1.13人/日に増加しました。(相対増加率64%) 増加は12月迄継続しました。(1~4月の15.6人/万人→5~12月の21.3人で37%増加)
切除率は、前4か月は月平均7件/10万人が、後8カ月も同様でした。検査を受けた3万3千人余に限ると、検査後60日内の手術実施率は前4か月の10%が後8カ月は7%と減少しました。検査を受けた人はかなり増加しましたが、予防的切除を考慮すべき変異陽性の人は増えていなかったという結果でした。(ハーバード大、Sunita Desai他 BMJクリスマス号2017)
 予防的切除で予後は良くなるか
予防的切除で予後は良くなるか
前々回の記事で2002年から10年で3倍に増加したと述べました。この報告では乳がん特異的生存率及び全生存率に有意な改善はなかったとされています。即ち、予防的に両乳房を切除してもしなくても生存率に差が無かったということです。
 今後の日本のあり方
今後の日本のあり方
カナダ有数のがんセンターで働く内野三菜子氏の報告です。
「オンタリオ州では保険で賄われるが、遺伝子検査やカウンセリングに厳格な適応、基準があります。(たとえば検査の基準で日本は45歳以下だが、こちらは35歳以下等) ただ“心配だから”だけではだめ。日本でもいずれは保険適用が検討されるでしょう。日本の実情に合った形として普及、定着するにはもう少し考えなければならない事がありそうです。」と記しています。(KUROFUNet 2013年9月)
結局、この疾患について知識の普及と国民の理解を深めた上で、社会の合意が必要という事ではないでしょうか。
(文責篠原)
遺伝子検査 (誤)2000~3000円→(正)20~30万円
前々回の記事からご覧いただけましたら幸いです。
がん最新情報Ⅴ(続々)遺伝しやすい乳がんとは
 アンジェリーナ・ジョリーさんの手術後、何か変化あったか
アンジェリーナ・ジョリーさんの手術後、何か変化あったかジョリーさんの手記は2013年5月にニユーヨークタイムズ誌に掲載されました。その前後で検査を受けた人、切除を受けた人数に変化があったかどうかの調査報告が出ました。
対象は2012~13年に保険に加入していた18~64歳の女性953万人余人です。
遺伝子(BRCA)検査の受診率は掲載前の10万人当たりO.71人/日から後は1.13人/日に増加しました。(相対増加率64%) 増加は12月迄継続しました。(1~4月の15.6人/万人→5~12月の21.3人で37%増加)
切除率は、前4か月は月平均7件/10万人が、後8カ月も同様でした。検査を受けた3万3千人余に限ると、検査後60日内の手術実施率は前4か月の10%が後8カ月は7%と減少しました。検査を受けた人はかなり増加しましたが、予防的切除を考慮すべき変異陽性の人は増えていなかったという結果でした。(ハーバード大、Sunita Desai他 BMJクリスマス号2017)
 予防的切除で予後は良くなるか
予防的切除で予後は良くなるか前々回の記事で2002年から10年で3倍に増加したと述べました。この報告では乳がん特異的生存率及び全生存率に有意な改善はなかったとされています。即ち、予防的に両乳房を切除してもしなくても生存率に差が無かったということです。
 今後の日本のあり方
今後の日本のあり方カナダ有数のがんセンターで働く内野三菜子氏の報告です。
「オンタリオ州では保険で賄われるが、遺伝子検査やカウンセリングに厳格な適応、基準があります。(たとえば検査の基準で日本は45歳以下だが、こちらは35歳以下等) ただ“心配だから”だけではだめ。日本でもいずれは保険適用が検討されるでしょう。日本の実情に合った形として普及、定着するにはもう少し考えなければならない事がありそうです。」と記しています。(KUROFUNet 2013年9月)
結局、この疾患について知識の普及と国民の理解を深めた上で、社会の合意が必要という事ではないでしょうか。
(文責篠原)
2017年01月12日
がん最新情報Ⅴー(続)遺伝しやすい乳がんとはー
前回の記事からご覧いただけましたら幸いです
(続)遺伝しやすい乳がんとは
 遺伝子検査の対象者
遺伝子検査の対象者
日本乳癌学会は2011年に検査を受ける人の基準を次の様に出しました。
・乳癌本人の場合
45歳以下の発症 50歳以下で2度近親者内に2人以上の乳 癌、又は近親者に卵巣がんがいる人 トリプルネガテイブ(ER,PgR、HER2全て陰性)乳癌
・2度近親者内に上記に該当する癌患者がいる人
・家計内に変異が確認された人がいる人
等です。(詳細はhttp://hbocnet.com/)
ー検査を受けるかどうかはご本人の自由です。よく考えて決めましょう。-
 遺伝子検査・カウンセリングの受けられる施設
遺伝子検査・カウンセリングの受けられる施設
静岡県内では今のところ次の施設を確認しています。
・静岡県立総合病院「遺伝診療科」
・聖隷浜松病院「遺伝相談センター」
・静岡県立がんセンター「がん遺伝外来」
検査は血液検査ですが、保険がきかないので2000~3000円かかります。
詳細は各ホームページを参照して下さい。
 遺伝性乳癌や遺伝子変異のある人の心構え
遺伝性乳癌や遺伝子変異のある人の心構え
米国では増加しているとはいえ、健全な対側乳房も切除するのは日本では抵抗があるでしょう。温存手術でなく乳房切除にするのも一つの選択です。対側乳房の検索を怠らないことと、発症し易いとされる卵巣がんにも注意を払う必要があります。発症していない人は若い内(25歳位)から定期的に検査を受けると良いでしょう。
全ての人が再発したり発症するわけではありません。“備えあれば憂いなし”です。何といっても自己検診が大切です。自分で早期に見つける努力をしましょう。
(文責 篠原)
(続)遺伝しやすい乳がんとは
 遺伝子検査の対象者
遺伝子検査の対象者日本乳癌学会は2011年に検査を受ける人の基準を次の様に出しました。
・乳癌本人の場合
45歳以下の発症 50歳以下で2度近親者内に2人以上の乳 癌、又は近親者に卵巣がんがいる人 トリプルネガテイブ(ER,PgR、HER2全て陰性)乳癌
・2度近親者内に上記に該当する癌患者がいる人
・家計内に変異が確認された人がいる人
等です。(詳細はhttp://hbocnet.com/)
ー検査を受けるかどうかはご本人の自由です。よく考えて決めましょう。-
 遺伝子検査・カウンセリングの受けられる施設
遺伝子検査・カウンセリングの受けられる施設静岡県内では今のところ次の施設を確認しています。
・静岡県立総合病院「遺伝診療科」
・聖隷浜松病院「遺伝相談センター」
・静岡県立がんセンター「がん遺伝外来」
検査は血液検査ですが、保険がきかないので2000~3000円かかります。
詳細は各ホームページを参照して下さい。
 遺伝性乳癌や遺伝子変異のある人の心構え
遺伝性乳癌や遺伝子変異のある人の心構え米国では増加しているとはいえ、健全な対側乳房も切除するのは日本では抵抗があるでしょう。温存手術でなく乳房切除にするのも一つの選択です。対側乳房の検索を怠らないことと、発症し易いとされる卵巣がんにも注意を払う必要があります。発症していない人は若い内(25歳位)から定期的に検査を受けると良いでしょう。
全ての人が再発したり発症するわけではありません。“備えあれば憂いなし”です。何といっても自己検診が大切です。自分で早期に見つける努力をしましょう。
(文責 篠原)
2017年01月12日
がん最新情報Ⅴー遺伝しやすい乳がんとはー

がん最新情報Ⅴ 遺伝しやすい乳がんとは
日本の乳癌は2016年の新規患者数予測では約9万人で女性では1位です。12人に1人が生涯一度はかかるとされ、女性では一番気をつけなければいけないがんです。
 乳癌の手術治療
乳癌の手術治療がんが乳房に限局されていれば切除手術が中心になります。これには、癌を周囲組織と共に切除する乳房温存手術(3c以下が目安になります)と、全部取ってしまう乳房切除術がありす。両者の治療成績に差はありません。
最近温存手術で良い人が乳房切除を希望する人が増えています。理由は、残った乳房の再発が心配、術後の放射線治療を受けたくない等ですが、切除後の再建手術が保険でできるようになった事も大きいようです。
 両乳房を切除したアンジェリーナ・ジョリーさんの選択米の女優アンジェリーナ・ジョリーさんが癌の無い対側の乳房も切除した事が話題になりました。遺伝性乳癌と診断されて、将来90%近くの確率で再発すると判断されたからでした。
両乳房を切除したアンジェリーナ・ジョリーさんの選択米の女優アンジェリーナ・ジョリーさんが癌の無い対側の乳房も切除した事が話題になりました。遺伝性乳癌と診断されて、将来90%近くの確率で再発すると判断されたからでした。1998年∸2012年に49万余人の乳癌を調査した外国の報告では、対側の乳房も切除した人は、2002年の3.9%から2012年には12.7%と3倍に増えました(Ann.Surg.Mar.2016)。米では予防的な切除は選択の一つとしてあたりまえになっていると言えそうです。
 遺伝性乳癌とは
遺伝性乳癌とは乳癌患者の5~10%の人にBRCA1/2遺伝子に変異が認められ、切除後も再発率が高いことが判っています。これを遺伝性乳癌といいます。再発の危険性は一般乳癌の3~4倍で、5年以内の再発率は12~20%です。未発症の人ががんになるリスクは40歳で10~20%、60歳で30~45%と高いです(日本乳癌学会HBOC班研究2009年)。
この遺伝子変異は親から子へ50%-2人に1人-の確率で伝わるとされています。この為本人だけでなく家族にとっても非常に悩ましい問題なのです。検査に際してはカウンセリングを受けて、十分に納得することが大切です。
2016年12月04日
がん最新情報Ⅳー肺がん検診は今のままで良いかー
がん最新情報Ⅳ 肺がん検診は今のままで良いか
 肺がんは死亡数で1位
肺がんは死亡数で1位
日本の肺がんは増え続けていて、平成12年以後死亡数はがんの中で1位です。喫煙歴の無い女性にも多いのです。次表のように2016年の予測でも新規患者数は3位、死亡数は1位です。患者の内57.8%もの人が亡くなります。胃がんの36.2%、大腸がんの35%に比べてかなり高い死亡率です。
肺癌予測数(国立がん研究センター 2016年)
新規患者数 死亡数 死亡率
男性 90600 55200 60.9%
女性 43200 22100 51.2%
計 133800 77300 57.8%
これは、早期発見が難しく、進行した段階で発見される例が多いことにも原因があるようです。発見時、早期の0~Ⅰ期(肺内で大きさ5cm以下、リンパ節転移なし)は40%ですが、Ⅲ~Ⅳ期(肺外に拡がり、遠いリンパ節や臓器に転移)は47%と約半分に昇ります。
全体の5年生存率39.5%、10年生存率33.2%という低さに予後の悪いことが現れています。肺がんはまだ完治のなかなか難しいがんと言えます。
 肺がん検診の現状と課題
肺がん検診の現状と課題
今日本の住民検診は胸部X線(一部検痰併用)が行われています。日本で行われた研究で死亡率減少効果が認められたことが根拠ですが、欧米での試験では認められず、日本だけのようです。
楠本氏(国立がん研究センター)は、X線検診の限界を指摘して楽観視を戒めています。「肺がんがあると判っている複数者による画像読影で平均26%の見落としがあった。」論文を基に、「誰が読んでも見落とすがんがある」と述べ、「毎年検診を受けていれば早期に見つかる」 「検診で異常ないからがんではない」は誤解で、限界があることを理解する必要があるとしています。(日本放射線学会 2016年)
検診発見のがんでもⅠ期は30%位にすぎず、5年生存率は75%に留まっていることに、専門家の嘆きと忸怩たる思いを感じます。
 低線量CTが薦められている?
低線量CTが薦められている?
このように現在のX線による検診は肺がん死の低減に不十分として、CTを薦める意見が多くなってきています。人間ドック等では行われてきましたが、住民検診ではその有効性が不確実として殆ど行われていません。
しかし、2011年に発表された「全米肺検診試験」はCT検診の有益性を広く知らしめました。これは55歳~74歳のヘビースモーカー5万3454人を無作為にX線群とCT群に分けた大規模なものでした。その結果、精密検査が必要な人はCT群24.2%、X線群6.9%、10万人年あたりの死亡数はCT群247人、X線群309人で、CT群で死亡率が20%低かったとしています。これに基ずき米国癌協会は2013年、ヘビースモーカーの高リスクの人や、禁煙して15年以内の人に毎年のCT検診を推奨しました。
この試験の問題点として、要精検率が24.2%と高く(日本では5%以下の報告が多い)、結果として無駄な精検を受けた人が多かったことが指摘されています。
 低線量CTって何?
低線量CTって何?
受診者の被曝線量はX線(1枚)で0.1ミリシーベルト(mSv)、一般のCT検査で6~10mSvです。最近のCTにはX線出力や管電流を管理コントロールする装置が付いていて、解像度を落とさずに1~1.5mSvで撮影できます。これでもX線の10倍ですので、さらなる改良が望まれます。
 日本のCT検診
日本のCT検診
日本でも自治体が費用を補助して行っている所があります。鹿児島県、和歌山県、日立市、北海道上川町などです。
鹿児島県の平成22年~24年度の集計結果を見てみましょう。
延総受診者17281人、要精検者2294人(要精検率13.3%)でした。この内59人にがんがみつかり(がん発見率0.34%)、41人(69.5%)がⅠ期の早期がんでした。
これと平成19年~23年度のX線検診との比較です。
受診者数 がん がん発見率
X線 709742人 374人 0.05%
CT 17281人 59人 0.34%
CTはX線に比べて6.8倍がんが発見されました。
 これから肺がん検診はどう受ける
これから肺がん検診はどう受ける
CTにより小さいがんが多く見つかることは明らかで、死亡率の減少が期待されます。しかし、小さい影が見つかったとしてもがんと必ずしも診断できるとは限りません。辛い精検(肺生検ー気管支鏡や体表から細胞を取って調べるー等)を何回もしたり、“がんかもしれない”不安をかかえながら経過をみる場合もあるかもしれません。
一方、X線では専門家も認めているように、見逃しがあることを知り、ある程度のリスクを覚悟しなければなりません。
それではどうしたら良いでしょうか。私はヘビースモーカーや40歳以上で血痰が出た人はCTとX線を交互に受けるのも一方法かと思います。(最初のCTで異常が無かったことが前提です。)被曝量が多くならないようにと、急速に進行するがんがあることを考慮してです。
決めるのは貴方自身ですよ!!
(文責 篠原)
 肺がんは死亡数で1位
肺がんは死亡数で1位日本の肺がんは増え続けていて、平成12年以後死亡数はがんの中で1位です。喫煙歴の無い女性にも多いのです。次表のように2016年の予測でも新規患者数は3位、死亡数は1位です。患者の内57.8%もの人が亡くなります。胃がんの36.2%、大腸がんの35%に比べてかなり高い死亡率です。
肺癌予測数(国立がん研究センター 2016年)
新規患者数 死亡数 死亡率
男性 90600 55200 60.9%
女性 43200 22100 51.2%
計 133800 77300 57.8%
これは、早期発見が難しく、進行した段階で発見される例が多いことにも原因があるようです。発見時、早期の0~Ⅰ期(肺内で大きさ5cm以下、リンパ節転移なし)は40%ですが、Ⅲ~Ⅳ期(肺外に拡がり、遠いリンパ節や臓器に転移)は47%と約半分に昇ります。
全体の5年生存率39.5%、10年生存率33.2%という低さに予後の悪いことが現れています。肺がんはまだ完治のなかなか難しいがんと言えます。
 肺がん検診の現状と課題
肺がん検診の現状と課題今日本の住民検診は胸部X線(一部検痰併用)が行われています。日本で行われた研究で死亡率減少効果が認められたことが根拠ですが、欧米での試験では認められず、日本だけのようです。
楠本氏(国立がん研究センター)は、X線検診の限界を指摘して楽観視を戒めています。「肺がんがあると判っている複数者による画像読影で平均26%の見落としがあった。」論文を基に、「誰が読んでも見落とすがんがある」と述べ、「毎年検診を受けていれば早期に見つかる」 「検診で異常ないからがんではない」は誤解で、限界があることを理解する必要があるとしています。(日本放射線学会 2016年)
検診発見のがんでもⅠ期は30%位にすぎず、5年生存率は75%に留まっていることに、専門家の嘆きと忸怩たる思いを感じます。
 低線量CTが薦められている?
低線量CTが薦められている?このように現在のX線による検診は肺がん死の低減に不十分として、CTを薦める意見が多くなってきています。人間ドック等では行われてきましたが、住民検診ではその有効性が不確実として殆ど行われていません。
しかし、2011年に発表された「全米肺検診試験」はCT検診の有益性を広く知らしめました。これは55歳~74歳のヘビースモーカー5万3454人を無作為にX線群とCT群に分けた大規模なものでした。その結果、精密検査が必要な人はCT群24.2%、X線群6.9%、10万人年あたりの死亡数はCT群247人、X線群309人で、CT群で死亡率が20%低かったとしています。これに基ずき米国癌協会は2013年、ヘビースモーカーの高リスクの人や、禁煙して15年以内の人に毎年のCT検診を推奨しました。
この試験の問題点として、要精検率が24.2%と高く(日本では5%以下の報告が多い)、結果として無駄な精検を受けた人が多かったことが指摘されています。
 低線量CTって何?
低線量CTって何?受診者の被曝線量はX線(1枚)で0.1ミリシーベルト(mSv)、一般のCT検査で6~10mSvです。最近のCTにはX線出力や管電流を管理コントロールする装置が付いていて、解像度を落とさずに1~1.5mSvで撮影できます。これでもX線の10倍ですので、さらなる改良が望まれます。
 日本のCT検診
日本のCT検診日本でも自治体が費用を補助して行っている所があります。鹿児島県、和歌山県、日立市、北海道上川町などです。
鹿児島県の平成22年~24年度の集計結果を見てみましょう。
延総受診者17281人、要精検者2294人(要精検率13.3%)でした。この内59人にがんがみつかり(がん発見率0.34%)、41人(69.5%)がⅠ期の早期がんでした。
これと平成19年~23年度のX線検診との比較です。
受診者数 がん がん発見率
X線 709742人 374人 0.05%
CT 17281人 59人 0.34%
CTはX線に比べて6.8倍がんが発見されました。
 これから肺がん検診はどう受ける
これから肺がん検診はどう受けるCTにより小さいがんが多く見つかることは明らかで、死亡率の減少が期待されます。しかし、小さい影が見つかったとしてもがんと必ずしも診断できるとは限りません。辛い精検(肺生検ー気管支鏡や体表から細胞を取って調べるー等)を何回もしたり、“がんかもしれない”不安をかかえながら経過をみる場合もあるかもしれません。
一方、X線では専門家も認めているように、見逃しがあることを知り、ある程度のリスクを覚悟しなければなりません。
それではどうしたら良いでしょうか。私はヘビースモーカーや40歳以上で血痰が出た人はCTとX線を交互に受けるのも一方法かと思います。(最初のCTで異常が無かったことが前提です。)被曝量が多くならないようにと、急速に進行するがんがあることを考慮してです。
決めるのは貴方自身ですよ!!
(文責 篠原)